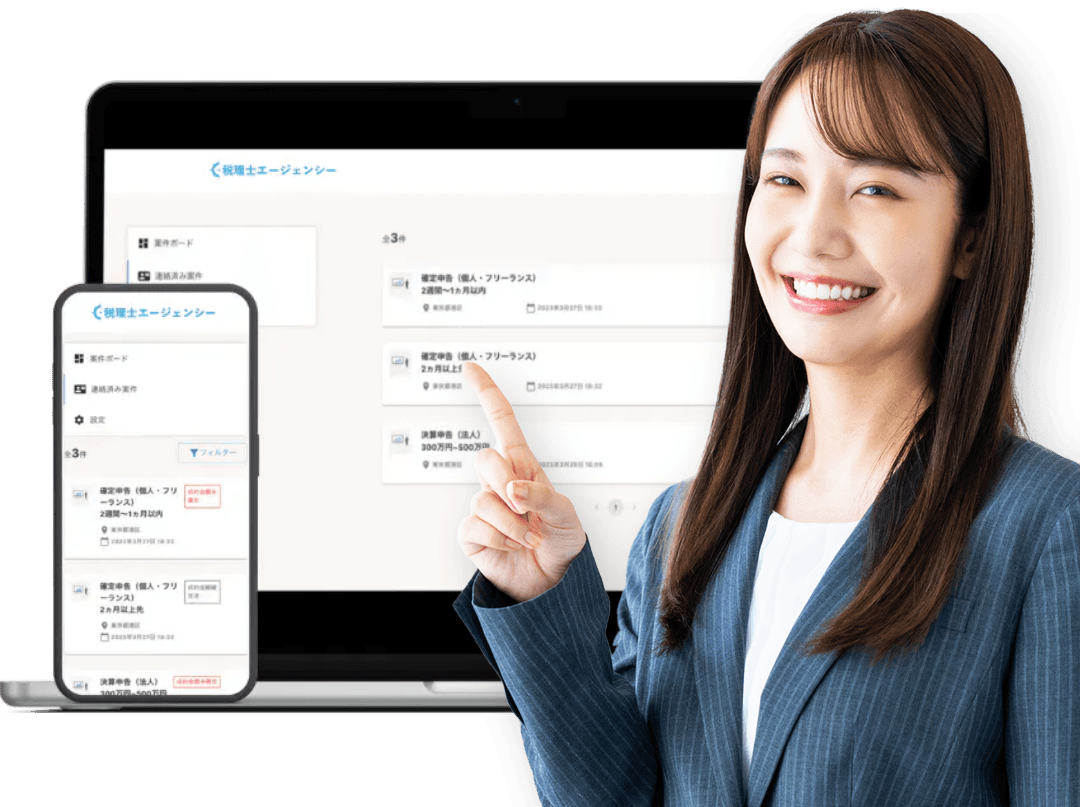
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。

日本では法人の80%~90%、個人事業主の20%前後に顧問税理士がいると言われています。
特に法人については、税務調査が入る可能性(噂では個人事業主の10倍とも言われています)や法人会計の複雑さを考えると、顧問税理士を付けることはマストだとも言えます。
顧問税理士にお願いすることで税務上のさまざまなリスクに対応できるようになります。
とは言え、顧問税理士についてよくわからないという方も多いはずなので、今回は顧問税理士の業務内容や税理士報酬の相場などについて解説します。
みなさまの仕事を理解し、しっかり対応できる顧問税理士に安く依頼できれば最高ですが、そのようなことは可能なのでしょうか?顧問税理士にお願いする部分と自分で行う部分をどこまでにするかしっかり判断して、さまざまな経営上、税務上のリスクを減らしていきましょう。
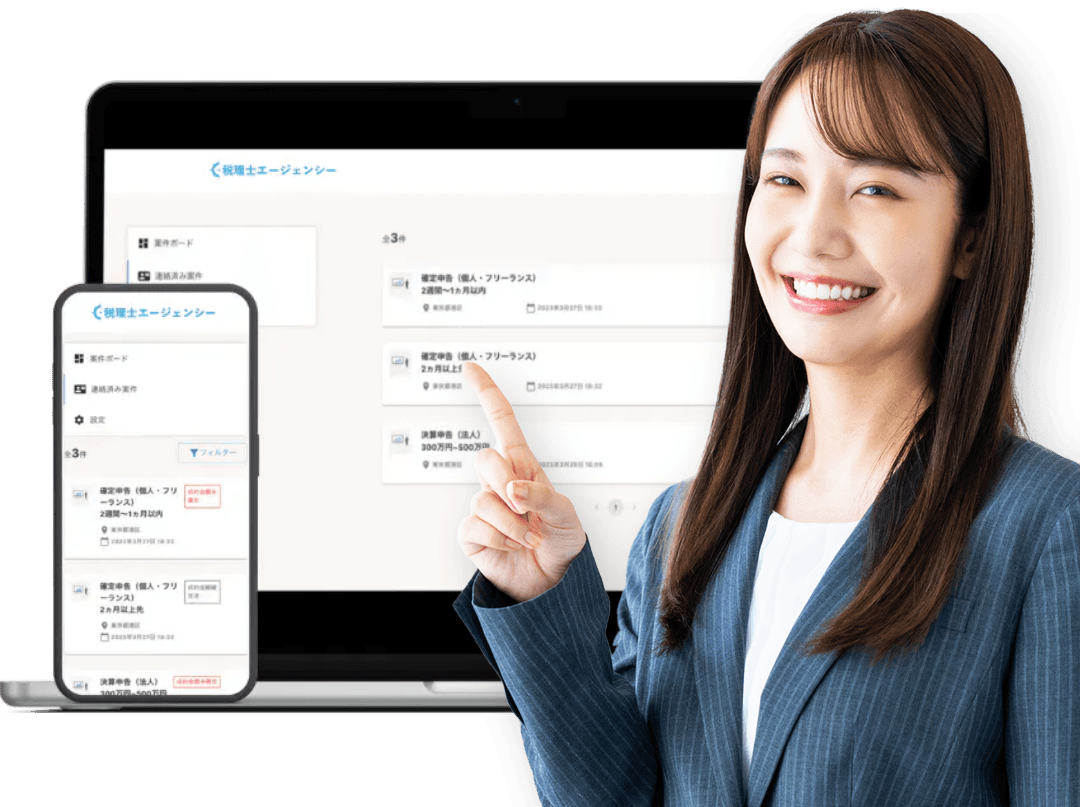
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
税務上のトラブルが起きたときに、単発で税理士に解決やアドバイスを依頼しても良いのですが、税理士の方も貴社の経営を熟知しているわけではないので困ってしまいます。
しっかり経営を理解し対応するために高額な税理士報酬を請求される可能性もありますし、継続的に経営を把握していないのでどこかで粗が出てしまう可能性があります。
顧問税理士にお願いする場合、毎月の顧問料(税理士報酬)を支払って、継続的に経営について見てもらっています。何かあったときの対応や、経費が支出に至った経緯など細かく把握しているはずです。
税理士と継続的な顧問契約を締結するとどのような業務を依頼できるのでしょうか?また月額顧問料の相場はどのくらいなのでしょうか?ここでは顧問税理士の基本的な知識について解説します。
以下にそれぞれ順に解説します。
顧問税理士にお願いできる業務は大きく分けると下記に分かれます。
どこまでお願いするのか、事前に顧問税理士とよく話し合ってください。依頼する業務が増えれば税理士報酬も高くなります。
毎月支払う月額顧問料に含まれるのは「日常的な会計処理等の会計業務のサポート」と「経営・財務分析・節税等の経営に関する相談」で、それ以外は別途報酬を請求されることが多いです。
事業を行う上で、日々発生する売上や経費の支払いなど会計処理が必要になります。税理士の指導で行われるので、当然複式簿記で仕訳を行います。
日々の会計処理や記帳、仕訳などは下記の2つのやり方があります。
当然、全部顧問税理士にお願いする契約をした場合、顧問料は高くなります。
自分たちで会計を行う場合、顧問税理士指定の会計ソフトを使います。クラウドソフトで、税理士側からもアクセスできるタイプが一般的です。弥生会計やマネーフォワードならば、マニュアルも販売されているので誰でも入力できるはずです。
自社のお金の流れ、キャッシュフローを知る意味でも、できるならば全部税理士にお願いせず、自分たちで会計、仕訳することをおすすめします。仕訳や勘定項目で迷った場合、顧問税理士に聞けばOKで、これこそが顧問税理士の日常業務です。
経費として計上して良いものダメなもの、経費の勘定科目や家事按分などについても適切なアドバイスが受けられます。期末に慌てて会計をして困ってしまうことはなくなります。
ただし税理士によってはメジャーなクラウド会計ソフトではなく、誰も知らないマイナーな会計ソフト(非クラウドタイプ)を指定する場合があります。これは「税理士ガチャ」外れになります。
おそらく地元税理士会などの利権で使っているソフトで、使い勝手が悪く、みなさまにメリットはありません。手間がかかりサポート体制も脆弱です。
顧問税理士契約を締結する際に、利用する会計ソフトについて聞いてください。特に税理士にすべてお任せしない場合、軽々ソフトによってこちらの負担が大きく変わります。誰も知らないマイナーな会計ソフトを指定する場合は、顧問税理士契約しないという選択も現実になります。
法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税、さらに法人、個人事業主ともに消費税の申告については、顧問税理士が行います。税理士が確定申告書を作り、みなさまがチェック後、税理士が申告(おそらく電子申告)します。
税務申告は本人か税理士(公認会計士含む)のみが行える業務です。
申告時の納税はみなさんが行います。あらかじめ、口座引き落としや予定納税しておくのが一般的です。税理士が納付書を作成し、みなさまが納付後申告を行うこともできます。
納税方法については顧問税理士の指示に従ってください。税の専門家が申告するので、ミス(申告漏れ等)もないはずです。
余談ですが、税理士が申告した場合とみなさま個人で申告した場合では、後者の方が税務調査を受けやすいという話もあります。税務署からすると、専門家(税理士)が立ち会わない、税理士が監修して申告しない場合、当然申告漏れや経費の過剰請求を指摘しやすいわけです。税務調査のさまざまなリスクを減らす意味でも、顧問税理士を付けて申告業務を行ってもらった方が良いでしょう。
税務上のさまざまな相談や経営に関するアドバイス、資金調達についてのアドバイスなどを顧問税理士が行います。税理士は税のことだけ、と思われがちですが、銀行など金融機関とのコネクションを持つ税理士も多く、資金調達全般や補助金や助成金についても相談できます。
脱税にならない「絶税」、キャッシュフローの流れ、経営コンサルティング全般のアドバイスも受けられます。
ただし、登記を伴う問題については、税理士ではなく司法書士の管轄になります。顧問税理士は司法書士とのコネクションもあるでしょうから信頼できる司法書士の紹介を受けてください。
法人の場合、3%~4%の確率で税務調査に入られると言われています。20年に1回と聞くとそれほどでもないかもしれませんが、それが来年かもしれません。
税務調査に入ると事務所から連絡があった場合、速やかに顧問税理士に連絡して、税理士とみなさまで事前準備を行います。また、税務調査時も顧問税理士が立ち合い、国税専門官とのやり取りも行います。
顧問税理士から事前に「言ってはいけないこと」「注意すべき発言」などの指示があるはずですのでそれに従ってください。大過なく税務調査を切り抜けられれば、それは顧問税理士が有能だったということになります。
従業員の給与計算や源泉徴収票の作成も顧問税理士の仕事です。給料から各種社会保険料や所得税、住民税を源泉徴収して従業員へ支払います。その計算や金額の確定を税理士にお任せできるのは、経営者にとっては非常にありがたいことです。従業員の給与計算業務や一部労務関連書類の作成を顧問税理士にお願いできます。
なお、下記は税理士ではなく社会保険労務士の独占業務です。
給与計算や年末調整については税理士が行えます。「労働」「保険」「年金」に関することは社会保険労務士、「税」に関することは税理士、「給料」は両方関係する内容です。
税理士と社会保険労務士のダブルライセンスを持つ人がいれば、全部その方にお任せできます。社会保険労務士についても顧問税理士から紹介を受けることも可能です。
突然経営者が亡くなった場合は相続が発生します。特に個人事業主や零細企業、家族企業の場合、子どもや配偶者に財産をどこまで相続するのかが問題になります。相続対応、および相続税の納税は大仕事になります。亡くなってから10か月以内に全部終わらせないといけないので、税理士の力が必要になります。
法人経営者が亡くなった場合も、経営者個人が持つ財産は相続となります。わざわざ別の税理士を探して相続手続きを依頼するよりも会社の顧問税理士にお願いして(別途費用を払い)手続きしてもらう方が良いです。
また不動産を売却した際には事業所得ではなく譲渡所得になり、分離課税として特別な申告が必要になります。税理士がいないと大変です。不動産売却の際には、税を控除できる特例がいくつもあり、税理士の力を借りて少しでも課税額が減るようにすることが大切です。
こうした事態にあたり、顧問税理士はとても頼りになります。通常の事業以外で収入があった場合の税務対応も顧問税理士の仕事になります。
顧問税理士に依頼する場合、月額報酬の相場は業務によりますが、3万円程度~10万円くらいになります。個人事業主と法人で異なりますが以下を目安にしてください。あまり高すぎるのも安すぎるのも不安です。
| 種別 | 事業規模 | 税理士顧問料月額相場 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 小規模(売上1000万円未満) | 5,000円~2万円 | 簡易な帳簿のチェックやアドバイス |
| 中規模以上(売上1000万円以上) | 2万円~5万円 | 毎月の帳簿チェック、総合的な経営アドバイス | |
| 法人 | 小規模(売上1億円未満) | 2万円~5万円 | 毎月の帳簿確認、試算表の作成、税務相談 |
| 中規模(売上1億円~5億円程度) | 5万円~10万円 | 経理サポートに加え、税務計画や財務アドバイスも含む | |
| 大規模(売上5億円超) | 10万円超 | 連結決算や国際税務など高度な業務も対応 | |
| 医療法人など特殊な法人 | 上記+5万円~20万円 | 専門的な会計にも対応 | |
これらは記帳代行を含まない場合です。記帳代行まで依頼する場合、月額顧問料は2倍以上になります。中規模法人以上の場合は経理部など経理担当者がいるはずなので、彼らに依頼することになります。中規模法人以上の規模で記帳代行や会計ソフト入力まで税理士にお願いすることになると、個人税理士ではなく税理士法人にお願いして金額もかなり高くなります。
個人事業主で年間売上1000万円未満(インボイス制度導入前は免税事業者)の場合、顧問税理士を付けることは稀です。個人事業主が顧問税理士を付けている割合は20%、小規模事業者に限定すればもっと割合が下がります。会計ソフト(個人事業主向け)を使えばそれほど記帳自体は難しくないので、あとは税務調査リスクなども考えて顧問税理士を付けるか決めてください。
なお、これは月額の顧問料です。
期末の法人税や所得税の確定申告の際には、「申告報酬」として別途月額顧問料の4~6倍かかるのでご注意ください。月額顧問料3万円の場合、1年間で支払う顧問料は3万円×12+3万円×6=54万円程度は見積もってください。
また税務調査が入る場合、「税務調査対応料」として1日5万円程度を支払います。日中顧問税理士が拘束されてしまうので、その辺りの補償も含みます。
代表者が亡くなるなどして相続が発生し、相続手続きや相続税の申告について顧問税理士に依頼する場合、報酬の相場は、遺産総額の0.5~1.5%程度になります。たとえば、遺産総額が5,000万円の場合であれば、税理士報酬は25万~75万円となります。別途発生する成果報酬なので注意してください。
顧問税理士を選ぶ際にどのようなポイントに注意すれば良いのか解説します。税理士は国家資格ですので「悪徳業者」のような人はさすがに少ないはずですが、それでもこちらの「足元」を見てくるかもしれません。また単純に能力的に疑問符が付く人かもしれません。
税理士は一度合格すれば、更新もなく生涯有効な資格ですので、最新の税制や税務ソフトにアップデートできない人もいます。そうした人を顧問に選んでしまうと困ったことになるので、しっかり選ぶポイントを掴んでください。
以下にそれぞれ順に解説します。
月額顧問料がわかりやすくかつ明確であるかが重要です。
顧問税理士の報酬としては下記の4つからなります。
この料金体系が明確になっている税理士は、明朗会計で信頼できます。さまざまな用件で都度請求してくる税理士はあまり信頼できないかもしれません。
税理士はあらゆる業界に詳しいわけではありません。不動産業界に詳しい税理士なら、不動産売買に関する譲渡所得についてさまざまな特例を知っています。「裏技」や「特例」を知っていて業界慣習や業界動向に詳しい税理士の方が節税になり、税務調査の際にも頼りになります。
たとえば、不動産売買に関する所得計算では、以下のような特例があります。
これらの特例の違いや適用基準を把握している税理士が頼りになります。大家さんならば不動産業界に詳しい税理士を顧問にすべきです。これらの特例を知っているのといないのでは大きく異なります。数百万円単位で納税額が変わってきますので、ぜひ自社の業界に関する知識・経験・理解がある人を顧問税理士にしてください。
個人事業主として1人で税理士を行っている税理士と、税理士法人で多数のスタッフを抱えている税理士ではサポート体制が違います。
事務所規模が大きくスタッフが多い方がサポートが充実しているのは事実です。しかし、税理士報酬が高くなる可能性があります(スタッフの給料も稼がなければならない)。
個人事業主あるいは1人会社、1人法人でやっている税理士なら顧問料を抑えられるかもしれません。みなさんが用意できる報酬額と期待するサービスを天秤にかけて、どのくらいの規模の税理士事務所(税理士法人)に依頼するか決めてください。
規模が大きい方が良い、というわけではないことに注意してください。
何か困ったことがあったときに対応が丁寧ですぐに返事があるかどうかも選ぶべき重要なポイントになります。税務上困ったことがある、不動産売買や資金調達を考えているときにすぐに親切な返事がある税理士が好まれます。
とは言え、契約してみないとわからないかもしれません。事前に問い合わせるときの反応である程度確認するか、口コミを調べて評価するのが良いでしょう。Googleの口コミはある程度参考になります。
また「税理士ドットコム」などに寄稿しているとどのくらい丁寧な対応をしているかわかります。とりあえず顧問税理士候補の方について、名前で検索してみてはいかがでしょうか?
可能ならば事業を続けている間、同じ税理士、あるいは同じ税理士法人に依頼できると良いです。税務調査があったときの対応も、資金調達のアドバイスも継続して顧問を務めている方が、クオリティの高いサポートを期待できます。
合う、合わないはどうしてもありますので、こちらも口コミや事前の問い合わせを参考にしていただけると長期的な関係構築ができるかどうか、ある程度わかります。
事前のオンライン面談ができれば、税理士の雰囲気や人となりがわかります。可能な限り正式契約前に顧問税理士候補の方とコミュニケーションを取ってください。
何か購入する場合「相見積もり」を取るのと同様、複数の税理士事務所、税理士法人から条件や報酬を聞いて比較するのは重要です。
「ここがいい」と決めていても、それは先入観かもしれません。一度顧問税理士を決めるとなかなか途中で変更できません。特に会計ソフトのデータなどを新しい税理士に引継ぎできる保証はなく、そうなるとずるずる引きずってしまいます。
事前に何社か税理士事務所、税理士事務所からさまざまなことを聞いて、そのときに疑問点をぶつけてみてください。税務申告の報酬、税務調査の対応、イレギュラー時の対応など、毎月の税務顧問以外の内容や報酬についても確認してください。
価格以外の「相見積もり」も取り、比較しながら長い付き合いになるように税理士事務所を決めてください。
顧問税理士を付けて毎月顧問料を支払う契約をしなくても、確定申告のときだけ単発で税理士に税務申告代行を依頼した方が月々の顧問料がかからず得、という考えもあります。
小規模事業者の場合、税務上の問題も少なく、期末にまとめて記帳や会計ソフトを入力しても十分間に合うし、その業務も単発で税理士事務所に依頼しても良いのでは?と考える人もいるでしょう。
個人事業主で年間売上数百万円という人は、そもそも税理士に頼らず自分で会計ソフトに入力して申告しても大きな問題になりませんが、一定規模以上(年間売上1,000万円超)の個人事業主や規模を問わず法人の方は、顧問税理士を付けた方が良いと考えます。
以下にその理由について紹介します。
顧問税理士を付けることで、すぐに税理士に相談できます。一定規模の個人事業主や法人の場合、期末にまとめて会計を行い税務申告するだけでは済まなくなります。
日常的な税務会計上の問題、資金調達、補助金や助成金などについてすぐに相談できる専門家がいることで、経営上多様な選択肢を取れます。
経営上の意思決定に際して、税理士という専門家がアドバイスできる部分は非常に多く、単に税務申告や日々の会計処理だけが業務ではありません。
経営に関してよろず相談できるのは、弁護士でも司法書士でも社会保険労務士でもなく税理士です。日常的な経営上の相談が可能なパートナーとして顧問税理士の存在は非常に大きなものとなります。
都度別の税理士に相談していては、結果的に費用も高くなりますし、その税理士は貴社の事業内容や経営状態を知らないので的確なアドバイスができない可能性があります。
税務調査に入られると、それだけで数日何もできなくなります。何を準備すれば良いのかわからず、税務調査によって申告漏れや「経費として認められない」などの指摘を受ける可能性があります。脱税まで行くことは稀ですが、それでも追徴課税されてしまえば、大きなダメージになります。
申告に不備がある場合、税務署から目を付けられてしまうことにもなり、以前よりも増して税務調査を受ける可能性が高くなります。申告漏れ、脱税と指摘されないためにも、顧問税理士が日常的に記帳、会計についてチェックしておくことが大切です。単発で申告代行を依頼しても出された領収証や資料での短時間の判断になってしまいます。
経営の連続性を重視し、「この経費はこういう理由で」と理解してもらうためには税理士と顧問契約をして、毎月、日常的に会計処理について目を光らせてもらうことが大切です。
その中でキャッシュフローが滞っているなど経営上の問題が見つかれば、専門家の立場から税理士がアドバイスします。自分が気付かない経営改善についても、顧問税理士からリアルタイムでサポートが受けられます。顧問税理士は単なる経理係ではないことがわかります。
適切な申告、脱税をしないというのは事業者として当然の義務(国民3大義務の1つ「納税」)ですが、「節税」は合法です。税について詳しくないと、税制の抜け穴、裏技についてもわからず、基本に忠実な申告をしてしまいます。もちろん、それでも問題ないのですが、毎年変わる税制の中で各種控除、特例を活用すればもっと納税額を減らせるようになります。
複雑な税制を理解し、適切で合法な節税手段を見つけられるのは税理士です。顧問税理士と契約することで、月額顧問料以上の節税を実現できる可能性が出ます。
各種特例を顧問税理士が適用できれば、(わざと?)複雑になっている税制に対抗して、納税額を合法的に減らすことも可能になります。
日々の会計処理や記帳も顧問税理士にお願いする場合は、業務負荷が減ります。会計業務は時間がかかります。それをアウトソーシングして、本業に注力できれば売上も上がり事業拡大できます。
もちろん、期末の税務申告だけでも税理士が行うことで大きな業務負荷削減につながります。
大企業の場合は経理部を置くことがほとんどです。しかし、そうではない1人会社などで会計の人を雇うくらいならば、月額数万円で顧問税理士にアウトソーシングした方が、業務負荷削減、業務効率削減、人件費削減につながります。
少人数の素人で複雑な会計をするくらいならば、顧問税理士にお願いすることで、業務負荷を大きく減らし、会計上のミスをなくしていきましょう。
顧問税理士を付けないという選択肢ももちろんあります。特に年収数百万円の個人事業主では顧問税理士報酬で生活が圧迫されてしまう可能性もあります。この規模なら会計ソフトで十分ですが、一定程度以上の個人事業主や法人の場合、顧問税理士を付けずに1人で対応する、あるいは社内のみで対応することはデメリットが大きくなります。
以下に顧問税理士を付けないデメリットについて解説します。
素人が会計処理を行うことで、記帳ミスや本来経費で計上できないものまで計上してしまうなどの仕分けミスも生じます。あるいは経費で計上できるのに計上しないことも考えられます。
税金過剰申告の場合は自社が損するだけですが、逆の過少申告の場合税務称され申告漏れなどのペナルティを課されてしまいます。悪質な場合は脱税として行政処分や刑事罰の対象にすらなり得ます。
ペナルティを受ければ今後の経営に大きな悪影響があります。処分となれば公示され、取引先や外部顧客の知るところとなります。
このリスクは事業規模が大きくなればなるほどあります。税務調査も入りやすくなり、何らかの指摘を受ける可能性も上がります。毎月数万円の顧問料を支払うのが嫌で顧問税理士を付けなかったばかりに、はるかに大きな信用を失ってしまうかもしれません。
少なくとも一定規模以上の個人事業主や法人は、顧問税理士を付けずに内部で対応するデメリットが大きすぎます。
1人、あるは内部で税務・会計処理を完結させようとすると、正確性だけではなく時間がかかります。税務、会計のプロである税理士に依頼した方がはるかに正確に処理が可能です。
素人ががんばって、税務・会計業務を行ってもクオリティが低く、かつ時間がかかってしまいます。要するに「コスパ」が悪いので、結果的にいい加減で時間ばかり取られてしまい、本業に集中できず売上に悪影響が出る可能性もあります。何か税務会場のトラブルが起きた場合、自分たちで対応しようとするとじかんがかかりかつ適切な選択をできないかもしれません。
やはり専門家である税理士と顧問契約した方が、さまざまな専門的な内容について即時対応可能です。
最新の税制、さまざまな特例については税理士のところに情報が集まります。確定申告や会計上の特例だけではなく、補助金など資金調達に関する情報についても税理士に聞くのが確実です。
補助金や助成金は期限があり、それまでに事業計画を作成し、必要書類をそろえて提出しなければなりません。良い補助金を見つけたが、気付いたら締め切り数日前だった、では対応できなくなります。
顧問税理士がいれば、「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」の4大補助金だけでなく、他の補助金の情報も日々クライアントであるみなさまに顧問税理士が情報提供します。
みなさまの業種、業界向けの専門的な補助金や助成金、税制優遇措置などを聞けるのは顧問税理士が大きな情報源になるからです。補助金を獲得できれば数百万円、数千万円の返済不要な資金を調達できる可能性もあります。
ぜひ、顧問税理士を付けないと、将来的に役立つ大きな設備投資などを公的補助で受けられるチャンスを伸ばしてしまうかもしれません。数万円を浮かせるために数百万円、数千万円失うことになりかねません。
顧問税理士を探したい場合どのようにすれば良いのでしょうか?良い税理士の探し方をここでは8つ紹介します。費用がかからないものが多いので、複数チャレンジしていただいても構いません。
以下に顧問税理士の見つけ方を順に解説します。
税理士エージェンシーは、依頼者と税理士をつなぐマッチングプラットフォームです。依頼者は無料で利用できるサービスとなっています。現役の公認会計士や税理士が監修しており、完全無料でみなさまにふさわしい税理士をご紹介します。もちろん顧問税理士も探せますし、特定の事案のみ対応する税理士も紹介できます。
同種の他のサービスとは異なり、完全オンラインで手軽に依頼できる点が大きなメリットです。
「税理士エージェンシー」では、確定申告や決算申告、相続税の申告、資金調達、さらには補助金や助成金の申請など、多岐にわたる案件に対応可能です。顧問税理士候補も探せます。事業主様からの依頼案件は拡大しており、幅広いニーズにお応えします。
使い方は非常に簡単です。「確定申告」や「相続税申告」など、依頼したい内容を専用のフォームに入力して送信するだけです。
サイトには「顧問税理士」のボタンがあるのでそれを押した後に、以下の条件を選択、入力します。
①と⑫は文章を記入、②~⑪はチェックボックスを選択するだけで、複数の税理士に「顧問税理士の相見積もり」を依頼できます。
その後、複数の税理士から見積もりや提案が届きます。税理士の経験や人柄、報酬額などを比較し、みなさまの希望に合った税理士を選ぶことが可能です。
料金体系もシンプルで、「初期費用」「成功報酬」などは一切不要です。税理士への報酬のみでご利用いただけるため、何度でも安心してご利用いただけます。
サービス利用の流れは次の通りです。
税理士エージェンシーは、面倒な手続きや高額な費用負担にならず、みなさまにふさわしい税理士を見つけるためのマッチングサイトです。
見積もりまでは完全無料で条件が合わなければ断ることも問題ありません。ぜひ一度気軽に「顧問税理士」で依頼をかけてみてください。
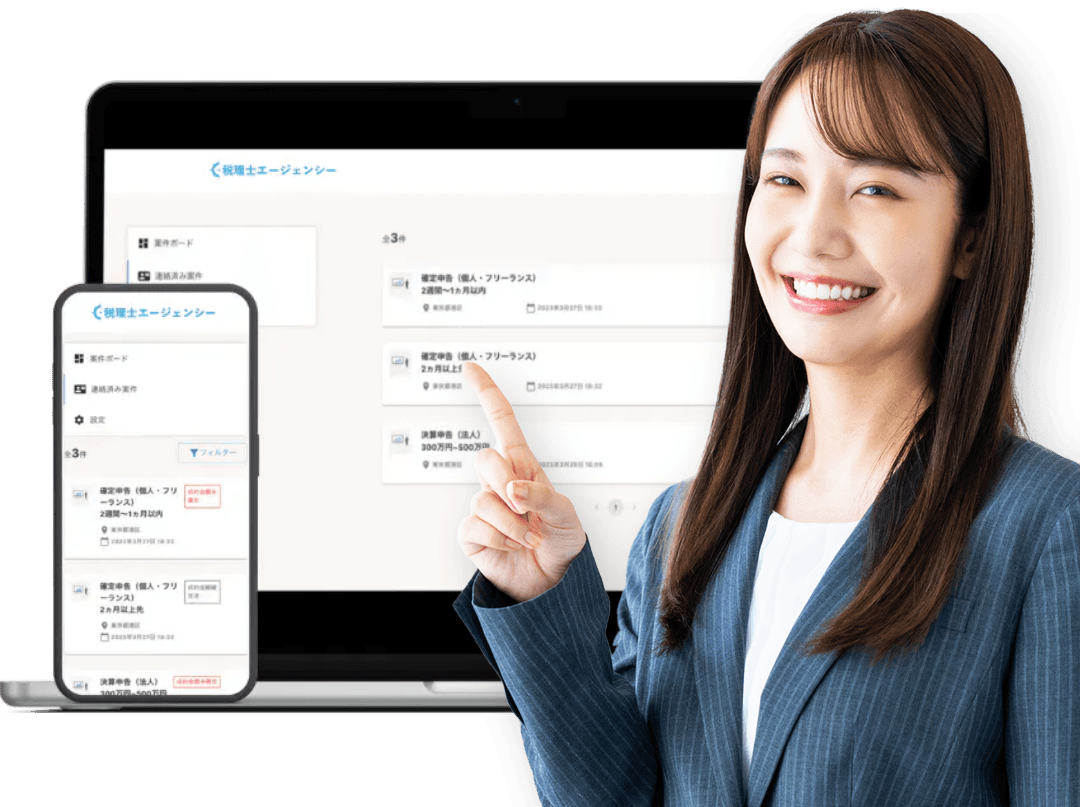
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
税理士団体である「日本税理士会連合会」や地域の税理士会のホームページには、所属している税理士が掲載されています。税理士の住所や年齢、得意分野や経験のある業種、業界なども掲載されているため、事業所近くでかつご自身の業種、業界に詳しい税理士をすぐに検索できます。
公的団体のホームページに掲載している税理士なら、「外れ」の可能性は低いはずです。ご自身で条件検索していただき、顧問税理士候補をぜひ見つけてください。
人伝で信頼できる税理士を紹介してもらう方法もあります。知人、友人からの紹介で「良い税理士」ということになれば安心できます。
ただし、人間相性がありますので、「知人にとって良い税理士だから自分にとっても良い税理士」とはならないこともあります。紹介してもらった税理士と合わず、契約しない、契約を解消する、対立してしまったなど問題があると、知人のメンツをつぶしてしまうことになりかねません。
紹介で上手く行けば良いのですが、そうでなかった場合、知人との関係も気まずいものになるかもしれず、しっかり経営判断をお願いします。
税理士会や商工会議所では定期的に税務相談会を無料で実施しています。そこで担当になった税理士に相談して、名刺をもらい個人的に継続指導や顧問契約をお願いすることもできます。
また、商工会議所の経営改善事業で「エキスパートバンク」というものがあり、税理士の個別指導を数時間、場合によっては数回にわたり無料で受けられます。そこで指導を受けた税理士と個別契約して顧問税理士になってもらうこともできます。
まず、お試しで税理士の指導を受けて、それで良い税理士だと判断できれば、顧問契約の交渉を継続して行えばOKです。
税理士会も商工会議所もお見合い仲人ではないので、事前に「こういう税理士がいたら紹介して」という個別対応は受け付けていない可能性があります。税理士無料相談や無料指導から、みなさんのイニシアティブで顧問契約へ進める必要があります。
金融機関と税理士の関係はとても密接です。金融機関が信頼できる税理士ならば、客観的にも有能な人でしょう。問題は、みなさんが金融機関から税理士を紹介されるくらいの付き合いをしているかどうかです。
まったく取引がない人から「税理士を紹介して」と言われても金融機関は対応できません。あくまで「お得意様」へのサービスです(税理士紹介は金融機関の業務ではありません)。みなさまが金融機関から信頼されていることが条件になります。
また、金融機関の「お得意様」になれるくらいの取引ということは融資金額も多いはずです。そのくらいの事業規模で顧問税理士なしというのはあまり考えられないかもしれません。
すでに顧問税理士がいるがあまり良くないと感じている。代わりの顧問税理士候補を金融機関に紹介してもらうの方が良いかもしれません。
「税理士ドットコム」や「ジャストアンサー」など税理士が一般の方からの質問に回答しているサイトがあります。回答を見るには会員登録や月額のサブスクリプションへの加入が必要ですが、税理士の名前くらいは無料で見られます。
そこから名前を見つけて検索して、その税理士のホームページやSNSを見つけて連絡を取ります。彼らは集客の意味でもこうしたサイトで回答していますから、問い合わせには真摯に対応してくれるはずです。税務上どのようなアドバイスをしているか、実際に確認できるので、得意分野などもわかりおすすめです。
遠方の税理士でもオンライン対応できる場合があります。問い合わせてみると良いでしょう。
地域の自治体でも税理士会や商工会議所と同様に、税理士の無料相談を実施しています。主に個人向けの税務相談(相続など)なので、法人の事業関係の税務相談は受け付けていない場合もありますが、個人の相談をした上で、「実は事業もしていてそれについては別途相談させてください」として、顧問税理士について個別交渉することもできます。
無料相談の税理士から名刺をもらえるのでそれを上手く活用してください。なお、同じテーマで複数回の無料相談はできないところが多いので、希望通りの税理士が見つけるかどうかはわかりません。税理士へのアプローチ方法の1つとしてご検討ください。
「ココナラ」「クラウドワークス」「ランサーズ」などのクラウドソーシングサイトでは、専門家へ仕事を発注できます。また、税理士が「顧問税理士になります」という仕事を掲示していることもあります。
各クラウドソーシングサイトで「顧問税理士」で発注検索すると、「顧問税理士になります」というサービスを提供している税理士が何名も見つかります。ここから契約して、顧問税理士になってもらえます。
多くのクラウドソーシングサイトでは、「サイト外での連絡や金銭のやり取り禁止」が定められていますが、顧問税理士になってサイト内だけでやり取りするのは正直あり得ません。
実際には連絡先を使えてそこから直接取引になるのでしょうが、この辺りのグレーゾーンについては自己責任でお願いします。顧問税理士の見つけ方として、クラウドソーシングサイトもあるということです。
顧問税理士に関してよく聞かれることについてQ&A形式でまとめました。ぜひ参考にしてください。
顧問税理士がいた方が良いのは事実ですが、売上が少額なのに毎月万単位の顧問料を支払うのは大変という個人事業主やフリーランスもいます。
最近は会計ソフトも良いものが増え、簡単に青色申告特別控除55万円(or65万円)の複式簿記ができるものが増えました。会計ソフト+顧問税理士報酬で年間10万円を超えてしまうと生活が厳しくなります。
個人事業主やフリーランスに税務調査が入る可能性は法人と比べて低いようですが、売上が急増している場合や年間売上500万円を超える場合(事業所得が300万円を超える場合)、比較的税務署にチェックされやすいようです(年間売上100万円でも税務調査が入る可能性は0ではありません)。
売上が急増している場合や年間売上500万円を超える場合、記帳は自分の会計ソフトで行い、月額報酬最低金額で契約して、いざというときに備えるでも構いません。
売上が2000万円を超えるような場合は、法人並みにチェックが入りますので、顧問税理士を付けることを検討してください。個人で不動産経営をしている大家さんは顧問税理士がいないと対応できません。ほぼ必須で顧問税理士を付けてください。
かかります。
毎年の所得税、法人税、消費税の申告や税務調査への対応こそが税理士に依頼する主目的です。
上記などは月額顧問料以外に発生しますのでご注意ください。
いずれも対応可能です。ただし月額顧問料の基本料金には踏まれず「オプション」とされることが多いです。
給与計算については、税理士事務所の多くは、給与計算代行サービスを提供しています。個人税理士に依頼した場合は費用が高くなる可能性があります。月額顧問料とは別に、従業員数や業務量に応じて料金が加算されていきます。
従業員数が多い場合は、それに比例して料金が増加します。
年末調整は、多くの税理士が対応可能です。特に法人や従業員を抱える個人事業主が依頼することが多く、年末調整の費用は月額顧問契約に含まれる場合と、別途請求される場合があります。従業員が増えるほど税理士報酬も多くなります。
住民税の申告もできます。そもそも所得税の確定申告をすれば自動的に住民税の申告をすることになります(所得税の確定申告は住民税の確定申告を兼ねる)。住民税の申告のみをする人は年金受給者などごく少数で、事業を行い顧問税理士を付けている人は対象外です。
というわけで法人の場合は会社の法人税申告とは別に役員の所得税申告、個人事業主やフリーランスの場合は通常の所得税申告をすれば、自動的に住民税の申告も税理士が行ったことになります。
住民税を普通徴収した場合は、個人で住民税の納付を行います。特別徴収を選択した場合は給料からの天引きになりますが、その手続きや計算についても顧問税理士へ依頼可能です。
給与計算、年末調整、住民税の申告、いずれも顧問税理士ができるので心配しないでください。ただし、別途報酬が発生することがあるのでご注意ください。
